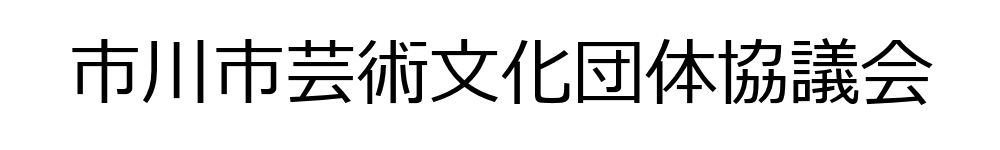| 事務局連絡先 | 事務局長宅 |
|---|---|
| 電話 | 047-334-7832(酒井方) |
| FAX | 047-334-7832 | 設立 | 昭和49年5月5日 | 加盟団体数 | 15団体〈令和6年10月現在〉 | 役員構成 |
会 長 : 能村研三 副会長 : 星 乗昭 稲葉 健二 酒井 玄枝 事務局長 : 酒井 玄枝 |
| 昭和20年 | 市川文化会が、戦後の枯渇した市民に音楽や美術を通して潤いと希望をもたらす目的で結成されました。 やがて幾つかの芸術文化団体を生んで解消しました。 |
|---|---|
| 昭和49年 | 芸術文化団体は年々発展し、団体数も増えると共に「文化都市・市川」としての発展を記する協議会設立のために、市川美術会の理事長藤野天光が率先して各団体に呼びかける事によって、市川市芸術文化団体協議会が設立されました。 | 平成4年 | 13団体が参加をして結成された協議会は、市内芸術文化団体の協議会として市川市文化向上の原動力となり、参加団体間や外部団体との研修・協議、市への建議等を通じて市民文化の振興に役立ち、その後、市川文化会館において、全日本文化集会千葉大会を開催し、主催者の一員として、市川市の文化レベル・当協議会結束の強さなど高い評価を得ました。 | 平成18年 | 芸術への第一歩「芸術ガイド」を発刊 |
| 役 職 | 氏 名 | 所 属 団 体 |
| 永世会長 | 村上 正冶 | 市川交響楽団協会 |
| 名誉会長 | 田中 甲 | 市川市長 |
| 相 談 役 | 内田 一孝 | 市川市花道協会 |
| 〃 | 臼倉 道代 | |
| 会 長 | 能村 研三 | 市川市俳句協会 |
| 副 会 長(総括) | 星 乗昭 | 市川交響楽団協会 |
| 副 会 長(事業) | 稲葉 健二(常任理事兼務) | 市川市芸能協会 |
| 副会長(渉外) 兼事務局長 | 酒井 玄枝 | 市川市合唱連盟 |
| 事務局次長 | 本池 美佐子 | 市川市俳句協会 |
| 会 計 | 伊東 美佐子(常任理事兼務) | 宗 左近・蕊の会 |
| 監 事 | 木村 珠美(常任理事兼務) | 市川オペラ振興会 |
| 〃 | 峰崎 進(常任理事兼務) | 行徳郷土文化緩和会 |
| 常任理事 | 渡邊 みどり | 市川市花道協会 |
| 〃 | 時田 雄 | 市川交響楽団協会 |
| 〃 | 湯浅 止子 | 市川民話の会 |
| 〃 | 須田 節子 | 市川市合唱連盟 |
| 〃 | 三沢 朋子 | 市川市洋舞踊協会 |
| 〃 | 町山 公孝 | 市川市俳句協会 |
| 〃 | 野竹内 康子 | 輪の輪工芸美術会 |
| 〃 | 笠井 晶子 | 装道礼法きもの学院千葉県認可連盟市川支部 |
| 〃 | 佐藤 和子 | 和心会~紫翠庵 |
| 〃 | 渡辺 成良 | 市川美術会 |
| 〃 | 今藤 政優 | 市川市邦楽連盟 |
| 理 事 | 林 恵美子 | 市川市花道協会 |
| 〃 | 篠田 要衛 | 市川交響楽団協会 |
| 〃 | 小林 路子 | 市川民話の会 |
| 〃 | 瀧本 安美 | 市川市合唱連盟 |
| 〃 | 荒木 さゆり | 市川市洋舞踊協会 |
| 〃 | 高橋 久美子 | 市川市洋舞踊協会 |
| 〃 | 成澤 香奈 | 市川市オペラ振興会 |
| 〃 | 藤城 俊悦 | 市川市芸能協会 |
| 〃 | 金田 径子 | 輪の輪工芸美術会 |
| 〃 | 後藤 幸江 | 装道礼法きもの学院千葉県認可連盟市川支部 |
| 〃 | 林 美和 | 宗 左近・蕊の会 |
| 〃 | 戸矢 晃一 | 宗 左近・蕊の会 |
| 〃 | 江口 愛理 | 和心会-紫翠庵 |
| 〃 | 松丸 陽子 | 市川美術会 |
| 〃 | 石引 美貴 | 行徳郷土文化懇話会 |
| 〃 | 板橋 幹男 | 行徳郷土文化懇話会 |
| 〃 | 杵家 弥江道 | 市川市邦楽連盟 |
第1章「総則」
第1条(名称)
本会は、市川市芸術文化団体協議会と称する。
第2条(目的)
本会は、市川市内における各種芸術・文化活動を行う団体の相互協力と理解を深め、本市の芸術文化の振興に寄与することを目的とする。
第3条(事務局)
本会の事務局は、会長宅に置く。
第4条(事業)
本会は、第2条の目的を達成する為に次の事業を行う。
(1)芸術文化団体の連絡提携
(2)会員相互の連絡及び情報交換
(3)芸術文化振興のための諸事業の実施ならびに協力
(4)他地域の文化団体との連絡提携
(5)その他本会の目的を達成するための事業
第2章「会員」
第5条(会員)
会員は、下記に定める団体会員、賛助会員から構成される。
(1)<団体会員>
芸術・文化活動を行っている団体は、法人、同好会、サークル等の名称に関わらず、団体として会員になることができる。
(2)<賛助会員>
団体会員に所属していなくても、芸術・文化振興に深い理解を示して頂ける方は賛助会員となることができる。個人の方や団体会員に所属している方も維持会員となって、芸文協を物心両面でサポートすることができる。
第6条(入会)
本会に入会しようとする団体会員は、入会申込書に必要事項を記入して、理事会にて提出。審査承認後に所定の振込口座に会費の振込みを確認した後、入会とする。賛助会員は入会申込書の提出と会費の振込みにて入会とする。
第7条(会費)
会員は毎会計年度、次に揚げる会員の区分により、それぞれ定める会費を納入することとする。
<団体会員>
12,000円 但し、年度会費の他に、事業運営の際に必要であると理事会で承認をうけた事業参加協力費を納入する。
<賛助会員>
1口2,000円(1口以上何口でも可)
第8条(退会)
本会を退会しようとする会員は文書により会長に届けでなければならない。
第3章「役員、常任理事、理事、担当者」
第9条(役員)
本会に次の役員を置く。
本会は、故村上正治氏を永世会長として戴く。
<役員>
・会長、副会長若干名、事務局長、事務局次長1名、会計1名、監事2名
<常任理事・理事>
・常任理事 各団体から1名、理事 各団体から2名以内
<担当者>
・広報担当者若干名、事業担当者若干名を置くことができる。
第10条(役員、常任理事、理事、広報・事業担当者の選出)
会長、副会長、事務局長、事務局次長、会計、監事は、総会において選出する。
2.常任理事・理事は各団体から提出された者により選出される。但し、会長、副会長、事務局長、事務局次長、会計、監事を出した団体は別枠とすることができる。
3.広報担当者、事業担当者は理事会にて承認を受ける。
第11条(役員の任期)
会長および役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない
2.欠員により補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第12条(役員、常任理事・理事、広報・事業担当者の職務)
役員の任務および権限は、次のとおりとする。
会長は本会を代表して会務を総括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
3.事務局長は本会の事務局を統括し、会長の補佐役として本会の事務が円滑に機能するよう事務局代表者として対外的な責任を有するものとする。
4.広報担当者は、藝文いちかわやホームページなどの広報に関わる業務を執り行う。事業担当者は、本会が主催、共催、後援する文化集会等の業務を執り行う。
5.会計は本会の経理を担当する。
6.監事は毎年度経理を監査し、その結果を総会において報告する。
7.本会は、役員と常任理事・理事をもって、理事会を開催して、会務の運営を行う。
8.本会は役員及び広報担当者、事業担当者で必要に応じて役員会を開催し、会の運営を協議する。
第13条(名誉会長・相談役・顧問)
本会に名誉会長、相談役、顧問を置くことができる。選任は理事会に諮り、会長がこれを嘱託する。
第14条(委員会の設置)
本会には、理事会が必要と認めたとき、各種の委員会を置き、実行委員を任命することができる。
2.実行委員は、理事会に出席して理事会の諮問に応じる。
第4章「会議」
第15条(種別)
会議は総会、理事会、役員会とし、会長がこれを招集し、会長が議長を務める。
2.総会は、定期総会および臨時総会とする。総会は役員、常任理事、理事が出席できる。
3.総会、理事会、役員会は会長が必要と認めたときに開催する。
第16条(会議の定足数等)
会議は、構成員の2分の1以上の者が出席しなければ、会議を開き議決することができない。但し当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者および他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席したものとみなす。
第17条(議決)
総会、理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、否同数のときは、議長の決するところによる。なお議決権は各団体一票とする。
第18条(会議の付議事項)
総会に付議すべき事項は、次のとおりとする。
事業計画および収支予算
2.事業報告および収支決算
3.その他重要事項
第19条(理事会の付議事項)
理事会に付議すべき事項は、次のとおりとする。
本会の運営に関する事項
2.総会に付議すべき事項
3.その他会長において必要と認める事項
第20条(役員会の付議事項)
役員会に付議すべき事項は、次のとおりとする。
理事会の運営に必要とされる事項
2.総会に付議する事項
第5章「会計」
第21条(経費)
本会の経費は、次の収入をもってあてる。
(1)会費
(2)寄付金
(3)補助金
(4)その他の収入
第22条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第6章「規約改正」
第23条(規約の変更)
この規約は、理事会および総会において役員の現在数の3分の2以上の議決を得なければ変更することができない。
第24条
この会則に定めるもののほか必要な事項は、会長が常任理事会の議決を得て定める。
付則
この規約は、令和7年4月23日から適用する。
昭和49年5月5日制定
昭和53年4月10日改正
昭和54年5月2日改正
平成2年7月27日改正
平成11年5月26日改正
平成13年5月30日改正
平成15年5月27日改正
平成16年9月25日改正
平成21年9月16日改正
平成23年4月27日改正
平成24年7月18日改正
平成25年4月24日改正
平成27年9月9日改正
令和7年4月23日改正